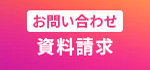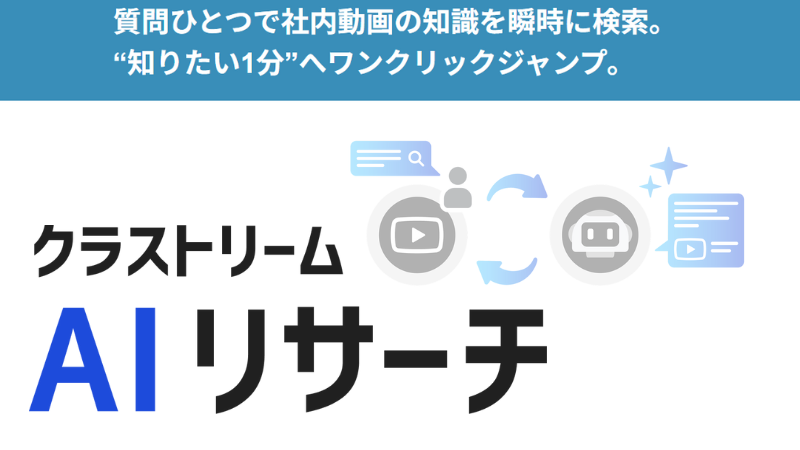2025/07/01
2025/06/30
【連載第1回】「見る」だけではもったいない!AIで企業動画を「ナレッジ資産」に変える方法【企業動画のAI活用】

目次
はじめに:あなたの会社の動画、本当に「活用」できていますか?
「今日の会議、議事録だけじゃなくて動画も残しておこう」「新入社員研修は動画で効率よく進めよう」。今や、多くの企業が日常的に動画を制作し、社内に蓄積しています。人事部が使う社内研修動画、現場で役立つ作業マニュアル動画、学習塾や資格学校が配信する授業動画、さらには社団法人が主催するセミナー動画など、その種類は実にさまざまです。
しかし、これらの動画、本当に「活用」できているでしょうか?
「動画はたくさんあるけれど、必要な情報がどこにあるかわからない」「結局、全部見ないと知りたいことが見つからないから時間がかかる」。そう感じている担当者の方も少なくないはずです。せっかく時間やコストをかけて作った動画が「撮りっぱなし」になり、その価値を十分に発揮できていないのは、実にもったいないことですよね。
動画は、単に「見る」だけのコンテンツではありません。実は、そこには企業の重要な知識やノウハウが詰まった「宝」が眠っています。この埋もれた宝を掘り起こし、企業の力に変える鍵。それが、近年目覚ましい進化を遂げているAI(人工知能)の活用です。
本記事では、企業動画が抱える現状の課題を明らかにし、AI技術がどのように動画を「見るもの」から「活用できるナレッジ資産」へと変革するのか、その可能性と具体的なメリットをわかりやすく解説していきます。
「撮りっぱなし」で終わる企業動画の現実と潜在的な課題
多くの企業で動画活用が進む一方で、以下のような課題に直面しているのが現状ではないでしょうか。
情報探索の非効率性
長い研修動画や会議録動画から、特定の情報を見つけ出すのは至難の業です。まるで大海原から針を探すようなもので、目的のキーワードで検索しても、動画の中のどこで話されているのか、正確な場所を特定するのは困難です。結果として、動画を頭から見直すことになり、大幅な時間ロスが発生してしまいます。急いでいる時に限って、なかなか欲しい情報にたどり着けない…そんな経験はありませんか?
知識共有の機会損失
ベテラン社員の熟練した技術やノウハウが詰まった作業マニュアル動画も、特定の部署や担当者しか見ることができず、全社的な知識共有に繋がっていないケースも少なくありません。新入社員や異動者が、必要な情報を自力で見つけにくいと、学習コストが増加し、スキル習得に時間がかかってしまいます。せっかくの貴重な知識が、一部の人にしかアクセスされず、企業の知識レベル全体の底上げに貢献できていないのは大きな課題です。
動画制作コストの回収不足
動画制作には、撮影、編集、機材の準備など、時間も費用もかかります。多大な投資をして作った動画が、一度見られて終わりだったり、一部の人にしか視聴されなかったりすると、投資対効果(ROI)が低くなってしまいます。動画の再利用や二次活用が進まないため、「作ったはいいが、思ったより活用されていないな」と感じる企業も多いのではないでしょうか。
企業動画を「ナレッジ資産」に変えるAIの力
これらの課題を解決し、企業動画の価値を劇的に高めるのが、AIの技術です。
AIが動画の価値を劇的に向上させる理由
AI技術は、私たちの想像以上に進化しています。特に動画関連では、以下のような技術が実用化されています。
- 音声認識(自動テキスト化): 動画内の会話やナレーションを自動で文字に起こします。
- 自然言語処理: テキスト化された内容から、キーワードや要点を抽出したり、文脈を理解したりします。
- 画像・物体認識: 動画内に映る人物、物体、文字などを認識します。
これらの技術が融合することで、AIは動画の中身を「理解」できるようになりました。これにより、これまで映像と音声の塊だった動画が、検索可能なデータとなり、これまで埋もれていた情報が可視化されるようになったのです。
「見る」から「活用する」へ:AIが可能にするブレークスルー
AIが動画の中身を「理解」できるようになると、動画は単なる「視聴コンテンツ」から、必要な情報にいつでもアクセスできる「データベース」や「ナレッジベース」へと進化します。これにより、「すべての動画が「ナレッジ資産」化」するという、まさにブレークスルーが生まれるのです。
AI活用で企業動画が「情報源」となる3つのメリット
AIを活用することで、企業動画は、これまでの課題を乗り越え、強力な「情報源」として機能し始めます。具体的な3つのメリットを見ていきましょう。
知りたい情報へ秒速アクセス:時間短縮と意思決定の迅速化
AIが動画の中身を理解することで、ユーザーは自然文で質問するだけで、AIが動画の該当シーンを秒単位で特定し、その部分の要約や字幕生成、さらにはタイムスタンプジャンプを即座に提示できるようになります。
例えば、「先月の定例会議で〇〇の進捗について誰が話していたか知りたい」と質問すれば、AIが該当シーンを特定し、その部分の会話内容と発言者を瞬時に教えてくれます。これにより、膨大な動画の中から必要な情報を見つけ出したり調べる手間をなくし、社内動画をフル活用できるようになるのです。これは、業務効率を劇的に向上させ、迅速な意思決定にも貢献します。
動画コンテンツの「見える化」:知識共有とスキルアップの促進
AIが動画の要点を自動で抽出し、簡潔な要約や重要なキーワードを生成することで、コンテンツの概要が即座に把握できます。これにより、長時間の動画を最初から最後まで見なくても、何が話されているのか、どこに重要な情報があるのかが一目でわかるようになります。
「要約も検索も学習も、AIが瞬時に解決提案」してくれるため、社員は効率的に情報を吸収でき、必要な知識をスムーズに獲得できるようになります。結果として、社員間の知識共有が促進され、組織全体のスキルアップにも大きく貢献します。
動画の多角的活用:ROI最大化と新たな価値創造
一度制作した動画は、AIの力で容易に再利用可能になります。例えば、過去の研修動画から特定のトピックだけを抽出し、新しいeラーニングコンテンツとして再編集したり、セミナー動画の内容を自動要約してブログ記事に活用したりすることが可能です。
これにより、動画制作にかかるコストの投資対効果が向上し、限られたリソースで最大限の価値を生み出すことができます。動画が単なる「記録」ではなく、常に価値を生み出し続ける「資産」となることで、企業の競争力強化にも繋がります。
> クラストリームAIリサーチで試してみる
御社の動画活用基盤は万全ですか?AI連携を見据えた最適な動画配信サービス選定の重要性
AIによる動画活用は、まさに未来の標準となるでしょう。しかし、AIの恩恵を最大限に受けるためには、まず動画を安全かつ効率的に管理・配信できる「土台」が不可欠です。
動画の「蓄積」から始まる活用フェーズ
動画をAIで活用するためには、その動画がしっかりと「蓄積」され、必要な時に安全にアクセスできる状態にあることが大前提です。膨大な企業動画を適切に整理し、スムーズに再生できる環境がなければ、AIの能力も十分に発揮できません。企業の動画コンテンツを安全かつ効率的に管理・配信するための最適なプラットフォームとして、クラストリームのような企業向け動画配信サービスがその役割を担います。AIとの連携を前提とした動画活用は、この「蓄積」フェーズからすでに始まっているのです。
セキュリティと拡張性が鍵を握るプラットフォーム選び
企業動画には、機密性の高い情報が含まれることも少なくありません。そのため、動画配信サービスを選ぶ際には、セキュリティ対策が強固であることが非常に重要です。特に、AI機能を利用する際に「お客様のデータをAIの学習に使用させない」といったプライバシー保護の観点は、安心してサービスを利用するための大きなポイントとなります。
また、動画活用の幅を広げるための拡張性も重要です。将来的にAI連携だけでなく、多様な機能追加が可能なプラットフォームを選ぶことで、長期的な視点での動画活用戦略を盤石にできます。**「すぐ使えて、情報セキュリティも安心」**という視点は、サービス選定において不可欠な要素と言えるでしょう。
まとめ:企業動画の未来を拓く「クラストリームAIリサーチ」の可能性
本記事では、多くの企業が抱える「動画の撮りっぱなし」という課題に対し、AIがどのようにブレークスルーをもたらし、企業動画を真の「ナレッジ資産」へと変革するのかを解説しました。
AIによる動画の要約、検索、タイムスタンプジャンプといった機能は、私たちが動画と関わる方法を根本から変え、「会議録や研修動画など、情報を引き出す“ナレッジパートナー“」として機能します。これにより、従業員は必要な情報に素早くアクセスでき、業務効率が飛躍的に向上します。
この革新的なAI機能が、弊社のクラストリームにオプションとして加わったのが、「クラストリームAIリサーチ」です。クラストリームAIリサーチは、これまでの動画活用における限界を打ち破り、動画コンテンツを最大限に活用することで、企業の生産性向上、従業員のスキルアップ、そして情報共有の加速を実現する強力なソリューションです。
御社の動画活用を次のステージへ引き上げ、真の「ナレッジ資産」へと変革するために、ぜひクラストリーム、そして革新的なクラストリームAIリサーチの導入をご検討ください。
> 他の企業活用例をみる(第2回記事:執筆中)